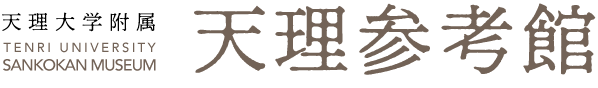天理ギャラリー展
第158回展「俳人蕪村-生誕300年を記念して-」
- 2016年05月15日(日)
第157回展「鉄道絵葉書の世界」
- 2015年10月22日(木)
第156回展「青銅のまつり ―光と音の幻想―」
- 2015年06月15日(月)
第155回展「手紙 ―筆先にこめた想い」
- 2015年01月22日(木)
第154回展「台湾庶民の版画・祈福解厄 ―幸せを願い、邪悪を祓う―」
- 2015年01月01日(木)
第153回展「古代東アジアの漆芸 ―東洋の美―」
- 2014年09月03日(水)
第152回展「漢籍と日本人 ―中国古典籍の伝来と受容―」
- 2014年05月18日(日)
第151回展 「蹴鞠 kemari」
- 2014年02月01日(土)
第150回展 「布留遺跡展 ―物部氏の拠点集落を掘る―」
- 2013年09月01日(日)
第148回展 「精霊との出会い ―西部ニューギニア先住民 神がみのかたち―」
- 2013年02月01日(金)