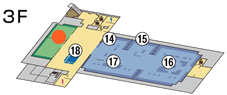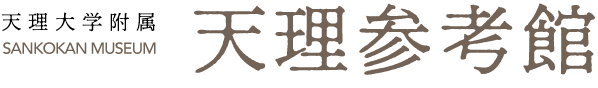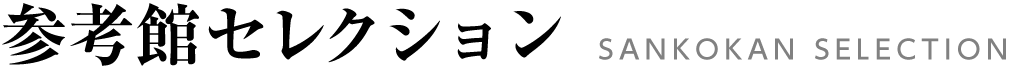こけし(中ノ沢系)
こけし(中ノ沢系)
こけし(なかのさわけい)






第99回企画展「こけしⅡ―遠刈田と土湯、中ノ沢―」に関連して、こけしをご紹介します。
別の記事でも紹介しておりますが、こけしは単一ではありません。産地ごとに形態や描彩に伝統的な約束事があり、師弟間で伝承された産地特有の技法のつながりを、こけし愛好家の間で「系統」とよび、現在は12系統を数えます。以前紹介した「土湯系」から分かれて、平成30年に12番目の系統を立てた「中ノ沢系」について今回お話いたします。
中ノ沢こけしは、福島県耶麻郡猪苗代町中ノ沢温泉を中心とする地域が主な産地です。大正時代末にこの地に来た岩本善吉(1877-1934)が作り始めました。善吉は他の多くの工人(こけしを作る木地師)たちのように、東北地方で代々木地屋を営んでいた家筋ではなく、栃木県の呉服屋の次男でした。親戚の芸妓屋に養子に入ってからは遊芸に没頭したといいます。兄の死で実家にもどりますが、わけあって25歳で上京して浅草で木地挽きを習います。努力を重ねて工場を経営するまでになりますが、第一次大戦後の不況で事業不振となり、福島県に移り住みます。土湯系工人にこけしのつくり方を学び、雇われた土産物店の注文を受けて51歳でこけしを作るようになりました。土湯系の特徴である頭頂部の蛇の目模様や胴のかたちは受け継ぎつつ、それまでなかった個性的な表情のこけしを創造します。驚いた瞬間の大きく見開いた目、利かん気をしめすような団子鼻、厚いくちびる、華やかな牡丹柄の胴模様など、今までなかったこけしでした。そもそも女の子を表現するとされ、穏やかな微笑みを浮かべるこけしを、後に親しみを込めて「たこ坊主」と称される、わんぱくな男の子のように作り上げました。
芳蔵(1912-1973)は善吉の息子です。昭和8年からこけしを作り始めますが、他人の模倣を嫌う父の影響で、独自の型を模索します(写真1)。昭和9年に善吉が亡くなった後に蒐集家から善吉型を熱望されますが応じず、昭和31年になってようやく善吉が創始した「たこ坊主」を再現しました(写真2)。当初の芳蔵型は頭が扁平で鼻が長く、善吉型に劣らず個性的であり、芳蔵のたこ坊主もまた魅力的です。芳蔵は弟子を多く育て、その後の中ノ沢こけしの発展に力を尽くしました。柿崎文雄(1947-)(写真3)は弟子の一人です。
1938(昭和13)年 全高30.3cm 岩本芳蔵(写真1)
1958(昭和33)年 全高22.0cm 岩本芳蔵(写真2)
1968(昭和43)年 全高21.2cm 柿崎文雄(写真3)