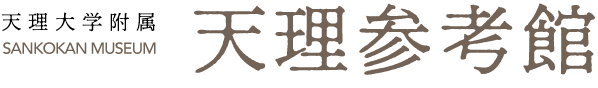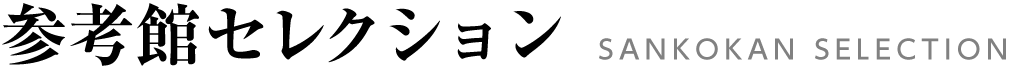方形三尊塼仏
方形三尊塼仏
ほうけいさんぞんせんぶつ


塼仏(せんぶつ)とは、仏の姿を彫り込んだ型に粘土を押し当てて型抜きし、焼成して作った仏像で、独尊像と三尊像があります。日本には中国の唐から伝来し、主に7世紀後半から8世紀に寺院の壁面装飾や信仰の対象として用いられました。奈良県飛鳥地域の寺院から多数出土しています。そのなかで橘寺と川原寺と壺阪寺から出土した、定印を結ぶ如来の左右に脇侍を配する図像の方形三尊塼仏は、図像が同形であり、共通の型を使って作った可能性があることが知られています。違いは、橘寺出土塼仏の四辺には5~6mm幅の縁が立ち上がっていることです。
この塼仏は出土地が伝わっていません。下半分しか残っておらず、多数の小さな穴が開いたりひび割れたりしていて、火災で熱を受けたような傷み具合ですが、上記の3寺院出土塼仏と同形の図像です。下辺にわずか3cmだけ縁が残っており、ほかの部分も縁が割れたような痕跡があります。左右の上角から約1.5cm内側には壁に取り付けるための釘穴が残っており、背景には白い着色が認められます。
釘穴と背景の白い着色も、橘寺出土塼仏に見られる特徴です。また『日本書紀』天武天皇9年(680年)4月条には、橘寺で火災があったという記述があります。以上のことから、この塼仏は橘寺から出土した塼仏の特徴と一致する点が多いといえます。
出土地不詳 7世紀 幅19.5 cm 土製
資料番号:2006A311